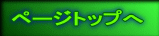羽津の昔「子どもの遊び」
3.昔の「だちん」
| やっこめ | ぐみの実 | |||
| あえだんご | さくらんぼ | |||
| ほとくろだんご | 桑の実 | |||
| だんご細工 | 山もも | |||
| 蒸しいもと焼きいも | モチツツジの葉 | |||
| 芋のかんぴんたん | イタドリ | |||
| 月見だんご | 野菜の生かじり | |||
| 麦こがし | 杏子 | |||
| あべかわ | 槇の実 | |||
| あられとかきもち | さとときび | |||
| 蒸しもち | ニッキの木の根 | |||
| 煎りそらまめ | 椎の実 | |||
| ズボート | ちゃせんぼ | |||
| 梅の実 | はすの実 | |||
| 筍の皮に梅干し | 花の密 | |||
| つばな | ゆず | |||
| シバの根 | その他 |
昔は、おやつのことを「だちん」とか「ちん」とか言っていた。育ち盛りの子供たちにとっては、三度の食事だけでは物足らず、何らかの間食を求めずにいられないのは、今も昔も変わらない。しかし、食べたい物は何でも食べられる今の時代とは違って、金を出して買った「だちん」は、滅多に食べさせてもらえなかった。若干の例外はあったが、凡そどこの家でも、似たりよったりの貧しさを抱えていたからである。
村の駄菓子屋や祭礼の屋台では、おたやんアメ、ねじがしん、つくばね、かんかんぼ、竹ようかん、金平糖などといったアメやセンベイを売っていたし、派手な女物の長襦袢を着流し、頭にはタライを乗せた姿のアメ売りや、「朝鮮は三徳商会、玄米パンのホヤホヤ」と呼売りにくるパン売りも来たが、よほどのことがない限り買ってはもらえなかった。
子供たちは、いつもひもじく口淋しかった。たまに美味そうな菓子を食べている子がいると、よだれが出るくらい羨ましかった。毎日の仕事に追われている母親にしてみれば、「だちん」を作って与える余裕はなく、そもそも作り方を知らなかった。
では、当時の子供たちは、どんな物を食べて口の淋しさをまぎらせていたのか。その一部を並べてみた。
やっこめ
苗代に蒔くための種籾は、発芽を促すために何日か水に浸しておくので、米はふやけてしまっている。この種籾の使い残りを土臼でひいて皮を取り、ふやかした米をホウロクで煎る。パチパチとはぜるまで煎った物を、餅や黒砂糖で固め、丸く握ったり四角に切ったりして食べた。香ばしい味がして、なかなかに美味かった。
煎った米つぶを砂糖で固めずに、そのままヒョウタンに入れて持ち歩き、そこから出して食べることもあった。
あえだんご
昔の団子は、今のように白米の粉ではなく、玄米のままをひいた粉で作ったので、黒っぽい色をしていた。
この団子の粉を練って丸めたものを茹で、そこへ黒砂糖を入れてからめたら出来あがり。
今の子供たちなら食べないだろうと思われる代物だが、昔の子供たちは喜んで食べたし、そう簡単には口に入らない上等な「だちん」だったのである。
ほとくろだんご
玄米を石臼でひいた粉で作った団子餅の中に、黒砂糖と米麹を茶碗に一杯ほど入れて搗く。そして、これを直径10センチくらいの棒状に丸めておき、柔らかい内に一口くらいの大きさに切ったものを陰干しにする。程よくく乾いた頃に、生のままで食べるのだが、遊びに行く時などには、これをほとくろ(懐)に入れて行くと、体の温みで幾分柔らかくなったように感じられた。
だんご細工
こねた団子の残りを少しもらい、これで鳥や動物など自分の好きな形のものを作った。そして、それをクドの火であぶり、ちょっと焦げ目がつくくらいに焼けたものを、フウフウと言いながら頬張った。
真ん中に黒砂糖を包んで焼くと、溶けた黒砂糖が団子に浸み込んで、更に美味かった。
蒸しいもと焼きいも
秋になると、その年に収穫したさつま芋ばかり食べていた。蒸したり、焼いたりして食べるのであるが、食べるには「二十日いも」とか「びんつけいも」と呼ばれる少し赤味がかった芋が美味しかった。
白い色をした「らくだいも」は、澱粉用に栽培された多収品種の芋で、食用としては味が落ちた。
焼きいもは、ドンドやクドの火に埋めておいたのを、頃合いを見て掘りだし、ホカホカを食べた。ちょうど「びんつけ油」のように粘りがあって甘い味がした。冬場まで保存しておいた芋は、さらに甘味が増して美味かった。
芋を食べたあとは、面白いくらいオナラが出た。芋を食べた者同士で、放屁の競争をしたり、尻のところへ手を回して捕まえたオナラを相手の鼻先ではなして喜んだりしたりした。
芋のかんぴんたん
蒸した芋を、ナガタンで適当な厚さに切り、日干しにしておくと、乾いて固くなり甘味が出てくる。これを、シコシコと噛むのであるが、腹を空かした子供たちが、充分に乾ききらないうちに食べてしまうので本物のかんぴんたんができあがることは少なかった。
月見だんご
毎年、9月の中頃になると十五夜お月さんが出るのを、子供たちは待ちあぐんでいた。
夕方になると、どこの家でもカド先に芒や萩をさした壺を立て、その前へ「とのいも」や「だんご」をお供えする風習があった。「お月さんはまん丸やな」 「兎のもちつきは始まっとるやろか」と話しながら、あるいは「十五夜お月さん見てはーねる」と歌いながら夜更けになるのを待っていた。今か今かと待っているのは長かった。月見だんごが欲しかった、食いたかった。
夜が更けて、その家の人が中に入ってしまうと、供えてあるだんごを食べた。他の家へも次々と廻って行った。
麦こがし
大麦を煎って石臼でひいた粉を、麦こがしと言った。この粉に黒砂糖を入れ、熱湯をかけて練ったものを食べた。
粉に、下白という安物の砂糖を混ぜて、そのまま口に頬張ることもあった。
あべかわ
煎った大豆を石臼でひくと「きな粉」ができる。これに、下白か黒砂糖の粉を加えて舐めた。
また、固くなった餅をゆで、これにきな粉をまぶして食べる「あべかわ」も、めったに食べられないものだっただけに、それこそ頬っぺたが落ちるくらいに美味かった。このあべかわは、今も作るし、土産物として売られているが、昔の方が美味かったように感じる。
あられとかきもち
これは、今でも作る家があるし、市販されてもいるが、昔は、だんごの粉の方が多くてモチ米は少ししか入れなかった。
これに、ちょっぴり砂糖を加えて臼で搗き、のし板で平らにのばしておく。そして、何日かして適当な固さになったら、これを切ってあられとかきもちを作り、更に乾燥させ保存する。
こうして作ったものを、煎ったり焼いたりして一年中の「だちん」にした。だから、子供の多い家では、十臼も二十臼もの餅をほぼ一日がかりで搗いた。
しかし、これも、常時食べられたわけではなく、雨の日など親が田畑に出られない時に、せがんでやっと煎ってもらった。
蒸しもち
これは、子供の「だちん」ではなく、臼で搗くモチと同じように祭事のときにのみ作ったいわゆる神饌であるが、子供としても、そのおこぼれにあずかるのを楽しみにしていたものである。
湯で練った小麦粉の皮に、餡子をつめた餅を、ガンタチ(いばら)やミョウガの葉で包み、蒸しあげたものである。ガンタチの葉で包んだモチは、今は一年中その辺の店で売られており、いつでも買って食べることができる。だが、昔は、これを作るのは田植えの後のサナボリ、天王さんの祭(小祭)、盆、新暦の9月1日にあたる八朔のいずれかだけで、それ以外の時には作らなかった。
つまり、年に一~二回しか食べられないとびきり上等のものであったから、これを作る日には、ろくに遊びにも行かず、セイロ蒸しをしているクドのまわりをウロウロして、早く出来あがらないかと待ちうけていたのである。そして、蒸しあがったモチを神棚なり仏壇なりへ献げたあと、ようやく許しが出て餅を頬張ると、舌もとろけるように美味かった。
煎りそらまめ
収穫後、乾燥させて保存したそらまめを煎って食べるのである。煎った時に、実がはじけたのはよかったが、皮をかぶったままだと、固くて剥くのに難儀した。
夏、海で泳ぐ時には、この煎りそらまめを入れた小さな袋を持っていく。そして、これを腰にぶらさげて泳いでいると、その間に豆に塩水がしみこんで美味くなり、固い実もふやけて剥きやすく、また噛みやすくなった。
ズボート
これは、声がよくなる薬といわれ、薬屋で売っていた。真黒くて断面がピカッと光る、ちょうど石炭の塊みたいなもので、これを二銭ぐらいで割ってもらったのを買ってきて、「だちん」がわりに舐めた。口の中に入れると、甘い味がして、なかなか溶けなかった。
大正の初め頃から、売られていたようだ。
梅の実
昔、羽津小学校から西の垂坂山までに民家は二軒しかなく、一軒は山のすぐ下で一軒は中程にあり、車井戸で水を汲んでいた。辺りは、見渡すかぎりの畑で、早春には梅の花の香りが学校まで漂ってくるほど、何処の畑にも梅の木があった。
その梅の木に実がなると、青いのもかまわずにちぎって食べた。そして、中にある固い種を割り、「天神さんが出る」と言ったりした。
筍の皮に梅干し
筍が芽を出す頃、これを剥いた新鮮な皮を三角に折り、その中へ梅干しの肉とかシソの葉を包んで、甘酸っぱい汁をチュウチュウと吸った。
筍の皮の表面は毛羽立っているので、これを庖丁の背や着物の袖で擦り落とし、梅干しやシソの葉を包んだ後、火鉢などで重しをかけ、折り目がきちんとつくと同時に皮が紫の汁の色でよく染まるようにした。そして、包みを開けて、誰のが一番よく染まっているかの較べっこもした。
梅干しやシソの葉のない時には、石垣の間などに生えている「かたばみ」の葉をとってきて、それに塩を混ぜながら石で潰したものを包んで、その汁を吸った。
つばな
五月になると、チワラ(茅)の穂である「つばな」を抜き取って食べた。
と歌いながら、両手にいっぱい採って、皮に包まれた絹のような白く柔らかい穂をむいて出し、その穂の先で耳のまわりを撫でてから食べるのである。
「おばけ」といって、穂が開ききり、あるいは紫色になったものは、食べると糞づまりになると言われていたので、用心して口に入れないようにした。
シバの根
「つばな」の出る茅のことを「チワラ」といい、これの根を「シバの根」とか「甘根」とか称して、噛むと甘い味がした。土の中から、白く細い根を掘りだすと、洗いもせず手で土をしごき落としたままで、口に入れて噛みみ、残りの繊維は吐き出した。
ぐみの実
6月中頃には、ぐみの赤い実が枝も曲るくらいたわわに生った。当時は、庭先に大きなぐみの木を植えた家が少なくなかったので、その木に登って食べあいをした。ぐみの実は、食べすぎると舌が荒れ、あとで痛い目をした。
秋に実のなる山ぐみもあったが、こちらは実の粒も小さく、かなり酸っぱい味がした。
さくらんぼ
米洗川の堤には桜の木がたくさんあり、飛びついたり登ったりしてさくらんぼを取って食べた。口やベロ(舌)を紫色にして帰った。
桑の実
夏が近づくと、あちこちの桑畑で桑の実が赤紫に熟しているのが目についた。それを見ると、一斉に畑の中へ飛び込み、「美味い美味い」と言って、競争のように食べた。手や口は真赤になり、着物についた汚れは、水で洗っても落ちなかった。
カバンから空になった弁当箱を出して、いっぱい詰めこんで帰るものもいた。あくる日になると腹くだりで、お尻がピイピイ鳴っていることもあったが、それにも頓着しないでまた食べた。
山もも
夏の初め頃になると、山ももの実が熟してくる。浄恩寺の鐘撞堂のすぐ横に、大きな山ももの木があって、実が鈴なりに生っていた。
この木に登り、猿のような格好で枝を折って食べていると、寺から出てきた老僧に「危ないぞ」と叱られた。しかし、美味い味が忘れられず、叱られても叱られても取りに行った。
モチツツジの葉
ツツジの花が散った頃、葉には餅のようにふくらんだ瘤がつく。これをむしりとって食べると、甘酸っぱい味がした。
決して美味いものとは言えなかったが、少しでも腹の足しになればと思って、何枚も葉をちぎっては口に入れた。
イタドリ
夏の初め頃、今のアスパラガスをぐんと大きくしたようなイタドリがまっすぐに芽を出した。これの若い芽を折りとって食べた。
折る時に、ポンと調子のよい音がしたら歯ごたえが柔らかく食べられたが、ぐにゃりと曲がって引きちぎらないととれないようなものは、スジが多すぎて食べられなかった。
体が震え上がるほど酸っぱいものだが、少し塩をつけると結構食べられ、いつも飢えていた子供たちの腹の足しにはなった。
野菜の生かじり
空腹を少しでも紛らすために、食べられるもので目についたものは、味の良し悪しは抜きにして片っぱしから食べた。
畑に作ってある大根、ナスビ、キュウリ、さつまいもなどは、取ったその場で生齧りにした。大根やさつまいもなどは、手で土を擦り落としたきり、前歯で皮をむきながら食べた。噛めば噛むほど甘い味がした。
時には、他所その畑にあるものを失敬して食べた。当時の大人たちは寛大だったのか、それとも失敬のしかたが巧妙だったのか、ふしぎと怒られなかった。
ナスビは、その年の初なりを軒先に吊るしておくと夏負けしないと言われていた。また、キュウリは、土用の丑の日に川へ流して疫病除けにした。
杏子
今は富士電機の敷地内に入ってしまっているが、昔の二区の三昧(墓地)にはかなり大きな杏子の樹が生えていた。この杏子の実が熟す頃、みんなで行っては、ちぎって食べた。
近頃は、杏子の樹など滅多に見ることができない。
槇の実
庭木や生垣にした槇の木で、よほど樹齢を重ねた木には、先端に青いまん丸の玉をつけた赤い実が生った。微かに甘い味はするものの取りたてて美味いというほどのものではなかったが、食べた。
また、先端の丸い玉をいくつも手に持って、ぶつけあいをしたりした。
さとときび(さとうきび)
これは、大抵の家で栽培していた。種を蒔いて育てるのである。そして、背が高く伸びて太くなった茎を節のところで切り、その皮をむいて噛むのである。
だから、さとときびのできる季節になると、子供たちのたまり場の周辺には、甘い汁が噛みつくして吐きだしたカスがいっぱい落ちていた。
さとときびには、長い穂が出て、たくさんの黒い実がなった。この実をとったあとの穂で「ほうき」を作って使いもした。
この他に、しぼり汁を煮つめて飴を作る「さとの木」というのもあったが、これは種蒔きではなく、根を埋めて栽培したもので、さとときびとは別の種類のものである。
ニッキの木の根
ニッキの木の根をしゃぶると、ぴりっと辛くて甘い味がした。「にぎわい場」などへ行くと、この根を小さく束ねたものを売っていたが、これを買えない者は、ニッキの木が植えてある家へ行って、根を盗み掘りして食べた。家の人に見つかると、木が枯れると言って、よく叱られたが、食い気に負けては掘りに行き、また叱られた。
椎の実
10月の祭の頃、学校の帰りに志氐神社へ椎の実を拾いに行った。夢中で拾っては、その場で食べたり、家へ持って帰りもした。
後から上級生が来ると良い場所をとられてしまい、しょんぼりと帰らねばならなかった。それほど上級生は怖かった。
椎の実は、生のまま皮をむいても食べられたが、家で「ホウロク」か「あられ煎り」で煎って食べると栗の味がして、とても美味かった。
ちゃせんぼ
秋の山へ行くと、黒っぽい紫色に熟した「ちゃせんぼ」の実がいっぱい枝についていた。これは、常緑の潅木で、「びしゃがき」とよく似ているが、実の粒は「びしゃがき」よりも大きい。
甘酸っぱい味がして、結構食べられた。
はすの実
葉が枯れ尽くした「れんこん田」には、蜂の巣みたいな形をし、カラカラに乾燥した蓮の実の殻が立っていた。これを採ってきて、中の実を取り出し、ホウロクなどで煎って食べた。
煎らずに生のままで食べることもあった。
花の蜜
代表的なのは、ツバキの花の蜜である。盛りを過ぎて地面に落ちかかった、あるいは落ちたばかりの花冠をとり、その裏にあいた穴に口をあてて、蜜を吸った。あんまり強く吸うと、黄色い花粉まで一緒に入ってきて、喉に引っかかるので、加減が必要だった。
その他、名前は知らないが、小さなラッパの形をした薄紫の野草の花をとって、その蜜を吸ったりもした。これは、ツバキよりも甘い味がした。吸ってみて、ちょっとでも甘い味がしたら、どんな花でもよかったのである。
ゆず
昔は、村のあちこちに、ゆずの木が植えてあり、冬になると黄色い実がたくさん生っていた。
ゆずの木には、鋭いトゲがあるので登ることは難しい。だから、長い棒を持って行って、下から実を叩きおとすのである。ゆずの実は、皮を食べるのが本来であるが、腹が減っている時には、中のものすごく酸っぱい実まで食べた。顔がひんまがるほど、酸っぱいものだった。
このゆずの皮からでる汁は、手足のヒビワレに効くといわれ、よく皮膚に塗りつけた。
その他
野いちご、木いちご、桃、ゆすら、ざくろ、すもも、瓜、西瓜、コウライ(とうもろこし)、いちじく、柿、栗、キンカン、夏みかんなど、四季折々に採れる自然からの豊かな恵みが、その都度子供たちの「だちん」となり、栄養ともなったのである。が、それらにしても年中あるわけではなく、また自家で栽培している果実については、親たちの厳しい管理下にあって自由に口へ入れられるものではなかった。
加えて、当時はどこの家でも子供の数が多かったから、それらを家族の中で分配すれば、一人に当たる量は知れたものとなり、充分な満腹感を得ることなどは夢みたいな話であった。
好き嫌いなど言ってはおられなかった。どんなに不味かろうと、口に入るものならば、片っ端から貪欲に食べたのである。
だから、ごく稀に美味しい菓子などが貰えた時には、それこそ頬っぺたが落ちるくらいに美味い味がしたものだし、すぐに食べてしまうのが惜しくて、長い間大事にしまいこみ、あるいは少しずつ嚙るようにして食べたものであった。